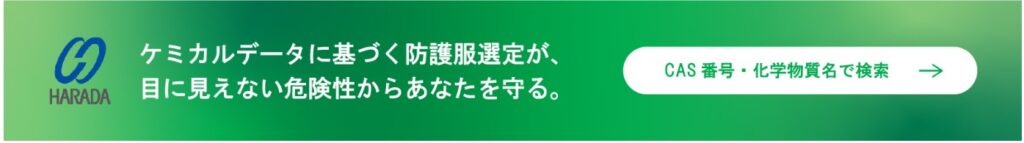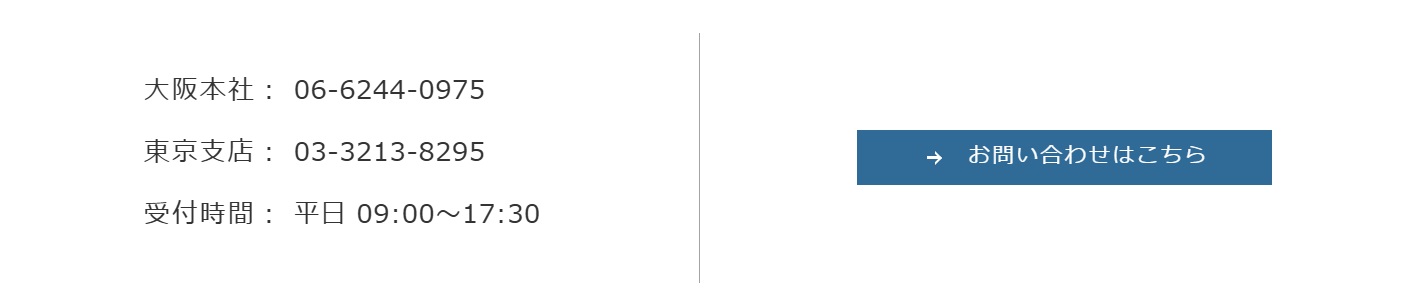化学防護服選定について
2024年4月の安衛法改正により化学物質リスクアセスメントで適切な保護具の着用が義務付けられました。
弊社ではLakeland社が持つ豊富なケミカルデータを活用し適切な化学防護服を選定出来るデータベースを公開しております。
2月は化学物質管理強調月間です。安衛法改正により、化学防護服選定時に発生している問題点をエンドユーザー様より伺う事が増えてきました。本コラムでは化学防護服選定時の問題点への弊社対応をまとめました。
1.オーバースペックな製品を選択してしまうケース
問題点
- 製品生地が分厚くなり作業性が低下
- 必要以上に余分なコストが発生
解決案
弊社Chem Max®シリーズでは他社では持っていない広範囲な耐化学薬品対応能力をもつChem Max®2をご準備しています。Chem Max®3の対象薬品70%カバーできる製品となり、オーバースペックを避け、コストを削減することが可能となります。
また、同じ生地を用いて前面のみ防護する場合のガウンや上半身のみのジャケットタイプなどニーズに合わせた幅広い商品を展開しておりますので、ご使用現場に最も適した製品を選んでいただくことが可能です。
2.現行品が実際に現場で使用している薬品への透過性能に十分対応できていないケース
透過データは、化学防護服を選択する際の重要なツールの1つです。
ほとんどのタイプ3の防護服の外観は類似しております。しかしながら、化学物質に対する透過耐性にはかなりのばらつきがあります。
問題点
透過時間が短く安全性が十分担保出来ていない。
- 例1)リユースの耐酸合羽や耐薬品エプロンの場合、浸透は抑えても透過してしまう。
- 例2)エレクトロ二クスで良く使われるフッ化水素/塩酸/IPA/硝酸など
解決案
・浸透と透過についての違いをご説明し、化学防護服見直しなど選定の際お役立ていただいております。
浸透と透過についての違いについては、説明動画を作成しております。下記ご参照ください。
・耐透過性データhttps://sf.haradacorp.co.jp/search/による豊富な薬品データを活用し適切な化学防護服をご提案します。
最後に
原田産業㈱セーフティープロテクションチームは、グローバルに対応する化学防護服を取り扱うLAKELAND社日本総代理店として、これからも皆様のお役に立てる情報を配信してまいります。
お困りごとなどあれば、お気軽に弊社担当者へご相談ください。
【厚生労働省皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル】https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001216985.pdf
【化学防護服製品サイト】製品情報 | 原田産業セーフティープロテクションチーム